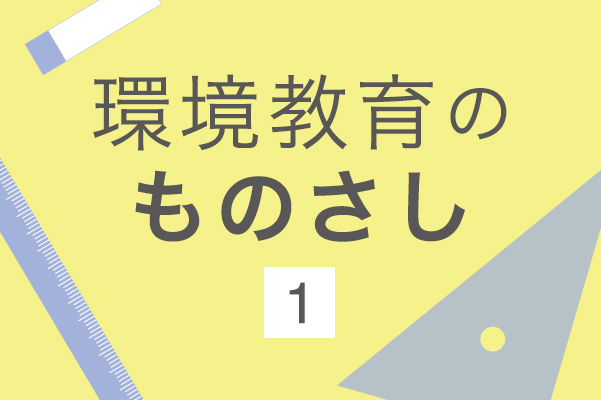
文:桜井 良(立命館大学)
環境教育の評価とは何でしょうか?教科書や関連資料をひもとけば、次のような説明がされています。
- 環境プログラムが与えるインパクト/効果を定量的・定性的に把握し、プログラムについて価値判断を加えること
- ミッションの進捗状況を把握し、改善点を見つけること
ただ、環境教育の評価を行ううえで、教科書に書かれていること以外に重要なことがあるような気がします。
プログラム運営者と共に考える
私にとって初めての評価に関する実践的な研究では、まず私自身がプログラムに参加し、内容について学びました。
その評価対象であった山梨県の「獣害対策普及啓発プログラム」の運営をしている地域住民のご夫婦の温かさと、獣害対策を通した地域づくりを目指す熱い想いを感じ、運営者を応援できるような評価をしたいと気持ちが変わりました。事前に作っていた評価項目は一旦わきに置き、ご夫婦と評価研究を設計し直すことにしたのです。
プログラムにかける想い、評価に期待していることなどを話してもらい、参加者への聞き取り項目を一緒に作成しました。研究の結果はロジックモデルにまとめ、論文だけでなくウェブサイトなどで公開することができました。
福島の復興支援員事業(※1)の評価に携わった時も、まずは地域の現状や支援員事業について理解するため、普及啓発事業を見学し、支援員一人一人への聞き取りを行いました。
その後、NPOや支援員たちと一緒に評価の設計を行い、住民への意識調査の内容を作成しました。その調査の結果、住民の支援員や復興への意識やニーズについて明らかにでき、支援員事業の中間的な評価(※2)をすることができました。
達成したいことを明らかに!
より良い評価を行うためには、まず、評価する側とされる側の間に、信頼関係を築くことが重要です。そのために、評価者はプログラム運営者がどのような想いで携わっているのかを、しっかりと学ぶ必要があります。そして、評価する側も評価で何を達成したいのかなどを明らかにすることが重要です。環境教育の評価とは結局、プログラム改善のために共に考える営みだと思います。
そして、皆さんが評価研究をする際は、まず
- ・何のために行う評価なのか。
- 評価結果を誰に見せたいのか。
- 評価結果をどのようにプログラム改善に活かしたいのか。
といったことを明らかにしたうえで、最適な調査手法・アプローチを選ばれるのがよいと思います。
- パートナーシップを重視したSDGsの推進〜目指せ!日本企業のSDGs実装元年〜
- 過去から学び未来に繋ぐ環境教育の形!(コスタリカ)
- パート3:開発途上地域(アジア)の地域デザイン第6回 〜拡大する都市と疲弊する農村部での地域づくりの展望〜
- 環境教育のものさし第1回 プログラム運営者の応援隊になろう!
- 考えるっておもしろいかも!? パート4:第2回 教育者としての軸
- 私たちの”選ぶ”が 社会を変える!
- 天然蜂蜜商品の流通・販売が着々と進んでいます!
- 行政と市民の各レベルから生物多様性保全の普及啓発を進めています!
- 読本『森里川海大好き!』が完成しました〜自然の中で輝く子どもたちを復活させるために〜
- SDGsを活用し地域活性化〜地方自治体からSDGsへのアプローチ〜
- SDGsってなんだろう?
カテゴリー
最新の記事
地球のこどもとは
『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。
私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。





