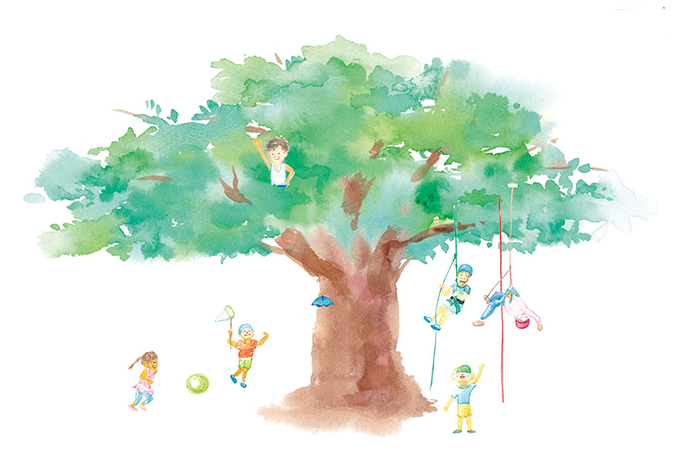
文:川嶋 直(JEEF理事長)
難しいからといって、諦めない
「環境教育の効果を測る」ことは非常に難しい。ここ数年内閣府を中心に「社会的インパクト評価」について議論が進み、今年に入って環境教育もその対象になっている。しかし、ある人にとっていつのどのような体験が、社会的な活動に結びついているのかを見極めることは、非常に困難なことだ。
計算が出来るようになるとか、英語が聞き取れるようになるなどと、測ることができる物差しがある場合には、教育の効果は測定が可能だろう。しかし、環境教育のように「意識の変化〜行動の変化」が期待される教育の場合にはその測定は非常に難しい。
ただ、困難なことだからと言って「効果を測る」ことを諦めるわけにはいかない。私達の教育的な意図を持った体験活動がどのような効果(その人の意識や行動の変化)を生むかを知りたいと思うのは当然のことだ。知りたいけど難しい。
今年から日本環境教育フォーラムでは立命館大学桜井良さん・東京大学中村和彦さんらと協働して、日本環境教育学会特設研究会「環境教育プログラムの評価研究会:「環境教育の評価学」の確立に向けて」という研究をすすめることにした。また、内閣府がすすめる「社会的インパクト評価」の検討会にも顔を出してメンバーとともに模索を続けている。
逆の視点から見る研究
「体験がどのような効果を産んだか」というベクトルとは逆の方向で「環境活動に熱心な人は、子供の頃どのような体験をしてきたのか?」という研究もあるようだ。私もその被験者(インタビューイ)になったことがあるが、過去のどのような体験が現在の自分に関係しているかを語ることは非常に難しく、つい聞き手(インタビュアー)の期待に応えようとその関係性を作ってしまう自分がいた。
ただ、以下のような体験はあった。自然学校で働く(これから働きたい)若者たちに「どうして自然学校で働きたいの?」とその動機を聞いた時に、多くの若者たちが「子供の頃の家族との山登りやキャンプなどの体験」を語ることが多かったことには驚いた。いや、あるいはこれも「聞き手(私)の期待に応えようとした」若者たちの配慮の結果なのかも知れないが…。

輝く姿に再会する時
今回「地球のこども」に寄稿いただいお二人は、私が1980年代から自然の中での環境教育プログラムを行っていた、山梨県清里のキープ協会のプログラム参加者だ。岩崎弘倫さんは大学生の頃とNHKに就職した直後に、玉井さんは中学生の頃に参加された方だ。お二人とも(なんと!)25年以上も前のことだ。つい最近お二人と20数年ぶりに再開してそれぞれの場で活躍していらっしゃる姿を知る機会があった。
「自然体験の効果」の証明は冒頭にも書いたように非常に難しいことだ。勿論今回寄稿していただいたお二人が「キープ協会での自然体験が今の活躍のベースになっている」などと言うつもりはない。ただ、最近のお二人の活躍を見て密かに目を細めていることは事実だ。多くの自然学校などの大人たちの喜びは、一緒に体験した子どもたちが成長して輝いている姿に再会することに他ならないだろう。これは、言うまでもなく教育をする全ての人に言えることだとも思うのだが…。
イラスト:高松敬委子
地球のこどもとは
『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。
私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。




