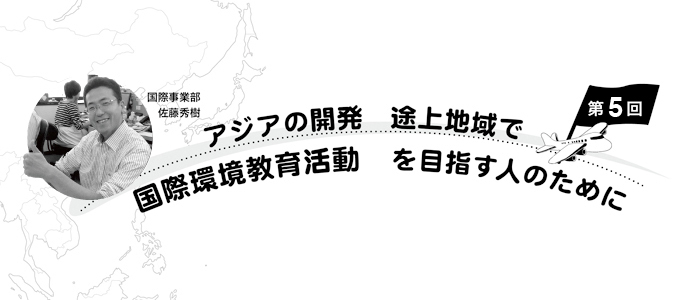
文:佐藤秀樹(JEEF職員)
日本での学びの場を最大限に活用
日本で、開発途上地域の環境問題を学ぶ講座・セミナー・シンポジウムや、ファシリテーション研修会等を通じて習得した知見や手法等は、国際環境教育活動を進めるにあたり、大切な第一歩になります。(独)国際協力機構(JICA)が運営する「国際協力キャリア総合情報サイトPartner(※1) 」や「国際協力マガジン(※2) を利用して、関心のある国際環境協力関連の学びの機会を探してみることをお勧めします。
国際環境教育というジャンルに特化した講座は少ないのが実情ですが、途上国の農村開発やコミュニケーションの取り方等、国際環境教育と関連する領域をカバーしているNGOや大学は多くあります。特に、国際環境教育の現場では、人との対話能力が求められるため、伝え方や傾聴の技能を磨くことが重要です。

小学校教員と生物多様性教材試行に関する意見交換(バングラデシュ)
現場での体験や実習を通じて、真のニーズを読取る能力を磨く
実践者を目指していくためには、自ら現場に足を運んで、現地住民や環境問題に従事する関係者・専門家と意見を交わし、議論していくことが必要です。
JEEFをはじめとして現場でインターンシップ制度をとっている環境および国際協力NGO等があります。そのような制度を利用して、実際の現場を五感で感じとることが、一番良い経験につながるものと思います。大学生であれば、大学の交換留学制度や、大学にきている留学生を通じて、現場へ一緒に連れて行ってもらう等、現場経験を積む機会を自ら切り開いていくことが必要です。
JEEFでは、2011年と2013年にそれぞれインドネシアで実施した、海外派遣研修のスタディツアー(※3)への参加も、現場を体験する良い機会になります。
当事者意識をもった眼で現地を見つめる応用力を培う
現場でのインターンやスタディツアーに参加する際、当事者意識を持って現地を見つめることが大切です。例えば、「地域住民の森林伐採を減らすためには、どのような方法や行動で意識を変えていけるのか」、「都市の効果的な廃棄物管理収集システムを行うにはどうすれば良いか」などを、現地の人たちの立場と視点に立って考えていくことが重要です。そのためには、短期間でも現地でホームステイをする等、一緒に日常生活を体験しながら暮らすことで、現場を観る応用力を培うことができると思います。

ごみ第一次集積場(バングラデシュ・クルナ市内)
現場体験で「使える」語学を会得する
アジアの開発途上地域でコミュニケーションをとるための手段として、英語は必須です。場合によっては、現地語の習得も必要になってくるかもしれません。語学は実践する中で、現場で「使える」語学能力を身につけることができます。最初は下手でも、現地の人と積極的にコミュニケーションをとっていくことが、語学の上達にとって不可欠です。現場を通じて会得した語学力は「使える」語学力となり、国際環境教育活動を推し進めていくための、極めて強い武器になります。
環境問題の真のニーズは、現地の人の声や現場踏査から読取ることができます。それらのニーズに対する解決へ向けた行動をとっていくことが、実践者として求められることであり、醍醐味であると思います。
国際環境教育の実践者を目指すのであれば、どれだけ多くの実践経験を積むことができるかが大切です。そのために日本での学びの機会を効果的に活用し、実践している人たちとのネットワーク作りを進めていくことで、現場へ足を運ぶ機会を増やすことができると思います。
※1 国際協力キャリア総合情報サイトPartner
http://partner.jica.go.jp/
※2 国際協力マガジン
http://devmagazine.org/
※3 海外派遣研修のスタディツアー
JEEFが実施したツアーは、長期:20日程度、短期: 10日程度。(独)環境再生保全機構・地球環境基金部が毎年主催。また、環境および国際協力NGOが独自で行っているスタディツアーもあります。
アジアの開発途上地域における国際環境教育活動にご関心がある・意見交換したい、インターンを考えている、一緒に協働プロジェクトを実施したい等がございましたら、お気軽にご相談下さい!
hideki_sato@jeef.or.jp
03-3350-6770
地球のこどもとは
『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。
私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。




