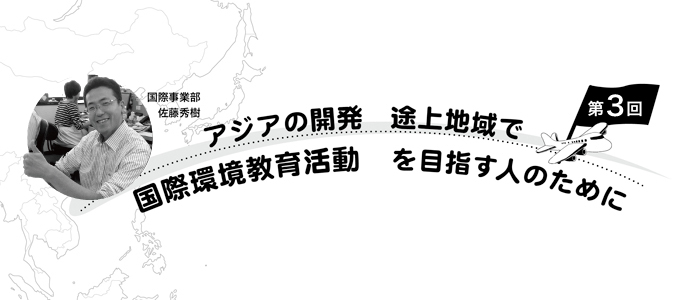
文:佐藤秀樹(JEEF職員)
第3回目は「国際環境教育活動が地域住民へもたらす影響と住民の自立発展性」について紹介します。 地域住民の環境保全の意識を高め、自立して持続的に地域の環境保全活動を進めて行くためには、どのような仕掛けや工夫が必要なのでしょうか。
1.途上地域における環境教育の重要性
途上地域の住民の生活は、都市でも農村でも環境と密接に結びついています。都市は、ごみや廃水の問題があります。農村部であれば、住民は農業、林業や漁業等の第一次産業に従事しており、地域の環境を守ることが、日常の生活に大きく影響を及ぼします。

水汲みにでかける女性(バングラデシュ)

自然と共生した暮らしが求められる農村の様子(バングラデシュ)
しかし、途上地域の環境問題に目を向けて見ると、環境問題を自分ごととして捉えることができていないのが現状です。その背景として考えられる一つの大きな問題は、「貧困」であり、その日暮らしをしている住民にとっては、環境の大切さについてわかっていても、環境を守っていく余裕がありません。
上述した通り、環境が日常生活を支えていることから、環境を破壊することは、貧困をより一層助長し生活の悪化につながります。環境、社会問題を解決していくためには、問題、課題を「自分ごと」として捉え、自分たちで責任を持って取り組むことが大切です。その重要性を認識する上でも、環境教育の力が大きな役割を発揮します。

ごみのポイ捨て(ベトナム)
2.住民の自立発展性を阻害する要因
途上地域での環境教育活動に当たっては、行政や援助機関等の実施する側と、住民の間には大きなギャップがあるように思えます。特に現地行政等のオフィサーは、依然としてトップダウン方式が強いことや、ワークショップマネジメントの能力不足により、住民の興味・関心を引出す活動ができていない現状です。また、住民との信頼関係が構築されておらず、相互の考え方に隔たりがあるように見えます。
そのため、実施する側は地域住民の立場にたって物事を観る力を身につけることが大切です。環境教育プログラムの中に体験的な学習を盛り込む等、お互いが楽しみながら信頼関係を築いていくための仕掛けづくりが重要です。
さらに、予算や時間、そしてプロジェクト成果や評価の視点から、環境教育に対する援助側の関心は薄く、長期計画が必要なこれらの事業は後回しにされる傾向があります。
住民側に目を向けてみると、地域の住民組織が脆弱であり、環境保全活動を継続的に行うための仕組みが構築されていないことや、「地域の環境リーダーが不足していること」が挙げられます。また、住民は何か援助をしてくれるのを待っている「援助慣れ」の傾向が強く、自立性が欠如していることも、地域での環境活動を持続的に行うことができない要因の一つとなっている場合があります。
3.住民が自立して持続的に地域の環境保全活動を進めて行くために
住民の自立性を高め、持続性のある環境教育活動を実現するためには、これまでの私の経験から、次の4つの視点で取組むことが重要であると思います。
- 住民の興味・関心を引き出すこと
- 協働で学習を深めること
- リーダーを育成すること
- 住民を組織化すること
住民が主体性や自立性を持つためには、実施者側が「住民の興味・関心」を引き出し、参加のきっかけをつくることや、住民や地域に十分なインセンティブをもたらす活動が必要です。
また、援助者が撤退した後でも住民の主体性によって活動が継続できるように、準備段階から援助者と住民の協働で学習を深めるための機会をもつことが重要です。さらに、住民の能力改善とリーダーの育成を行うことで、住民組織が強化されます。
このような仕掛けにより、住民の自立性と持続性のある、地域での環境教育の活動へとつながっていきます。

住民グループによる苗床の準備(インドネシア)
地球のこどもとは
『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。
私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。




