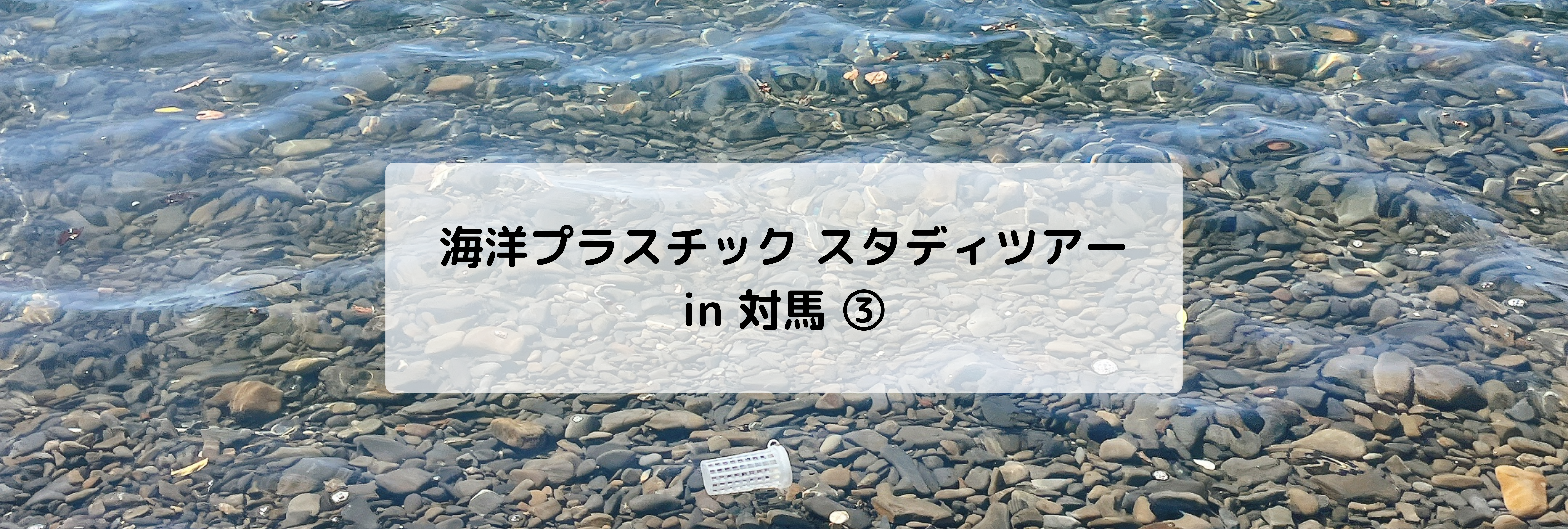
「横浜市における海洋プラスチック環境教育プログラム」をご支援いただいているジョンソン株式会社の皆さまと共に、対馬で2泊3日の海洋プラスチック体験ツアーを行いました。
対馬は、日本で最も海洋プラスチックごみが流れつく島と言われますが、実際に行ってみると想像していたよりもはるかにすごい光景が広がっていました。3日間の様子をダイジェストでお届けします。

3日目
最終日は、対馬の海と山の環境問題について学ぶ『持続可能な海と山を繋ぐ伝承ツアー』に参加しました。
案内してくださったのは、獣害問題に取り組む一般社団法人daidaiの齊藤ももこさん(左)と、磯焼け問題に取り組む有限会社丸徳水産の犬束祐徳さん(右)。海と山のプロがタッグを組んだ、画期的なツアーです!

こういったツアーができるのも、山が海に入るといわれるほど海と山が近い対馬の地形が関わっています。
漁船に乗って、深刻化している磯焼け現象を見学、そのまま半島に上陸し、山の課題や罠の説明などを聞くという、対馬ならではのツアーです。

まずは、沿岸に浮かぶ養殖場へ。ここでは、沖合の定置網にかかってしまったまだ売り物にならない小さな魚を大きくなるまで育て、出荷しています。
通常、未利用魚はリリースされるのですが、一度網にかかった魚は弱って死んでしまうことも多いのだそう。それであれば、しっかりと育てて命を無駄にしないという取り組みです。

続いて海の中を覗いてみると、磯焼けによって岩場だらけ。海藻を食べる南方系のイスズミやアイゴといった食害魚が海水温の上昇によって一年を通して活発化し、海藻を食べ尽くすようになったのです。

特に海藻を食べる量が多いイスズミは、内臓部分に強烈な臭いがあり、食用には適さないため、捕獲しても焼却処分にするしかありませんでした。
丸徳水産さんではこのイスズミに対する画期的な取り組みを行っているのですが、それはまた後程。

獣害から獣財へ
船で小さな半島に上陸して、獣害問題についても教えていただきました。
平地が少ない対馬では、集落から山を越えて行くよりも、船で海から乗り付けた方が便利な畑作地が結構あるそう。この日訪れたのも、以前は畑だったものの、高齢化や人口減によって耕作放棄地になっている場所。あちらこちらにシカやイノシシの足跡があります。

自然がゆたかで食べものや隠れ場所が多いため、シカがどんどん増えていき、今では対馬市の人口2.5万人よりも多い約4万頭が生息しているとのこと。
島内で捕獲に携わる方も増えてきているそうですが、今度はシカやイノシシの警戒心が高まり、島外から来たハンターが「こんなに獣が擦れている地域はない」と驚くほど、罠にかかりにくいそうです。

そうして苦労して捕獲したシカやイノシシですが、山から運び出したり、食肉加工するのは重労働。ハンターの高齢化が進む中で、山から運び出せずに埋めてきてしまうということもあるそうです。
そこで、齊藤さんは「獣害から獣財へ」をキーワードに、生きものたちの命をポジティブな循環へ導くことを目指し、罠の設置者から連絡をもらって生きものを回収に出向き、食肉加工して販売をする事業を行っています。

さらに、鳥獣被害対策のコンサルティングや研修、子どもたちへの普及・啓発も行っています。
実際に近年対馬では若手のハンターが増えてきているとのこと。これからの変化にも期待です。

食べる食害対策
冒頭でとっておいた丸徳水産さんの食害魚対策の取り組みですが、それはおいしく食べること!
イスズミは、別名“ねこまたぎ“と呼ばれ、猫でも食べないほどおいしくない魚と言われていますが、試行錯誤を重ねて魚肉のメンチカツ(そう介のメンチカツ)に。その味は、料理コンテストでグランプリを受賞するほど!

開発者の丸徳水産専務・犬束ゆかりさんに開発のお話を伺いました。
実際においしいとなると食べてくれる人が増え、イスズミが減って、磯焼けが起きていたエリアに海藻が生え始めたりもしてきたそうです。
最終日のお昼ご飯は、3日間のふりかえりのような気持ちでいただきました。

海洋プラスチック問題の最前線について学びに行った対馬ツアーでしたが、それ以上に学びの多い3日間を過ごすことができました。
きれいな海を取り戻すために、わたしたちにできることをこれからも考え続けていきます。

※このプログラムは、ジョンソン株式会社からの寄付金によって支援されています。
文責:鴨川光




